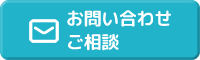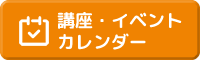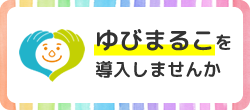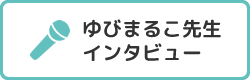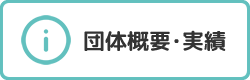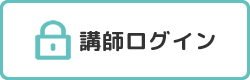- ホーム
- 心を育むゆびまるこ日記
心を育むゆびまるこ日記
こころのアートで、思い込みをはずす。
2024/06/28
「わたしはカタチを描かないといけないと思い込んでいたんですね」


こんにちは。
心を育むパステルアートゆびまるこのルパです。
アートセッションでのできごと。
アートセッションではプライベートの時間。
お話をしながら、その日のアートを描いていきます。
お一人お一人、思いが違うので
その時にあった、話しの流れでアートのテーマが決まっていきます。

今回は陶彩画草場さんの展示を見たシェアから。
陶器に描かれた絵画の世界は角度によって、時間によって
色が変わり、絵が変わっていったのだとか。
それがとても感動的でしたと。
「絵に添えられた言葉がこころにはいってきました」
こころには、絵だったり、色だったり、言葉がスッとはいってくる。
はいってきた言葉がいま、必要なメッセージなのでしょうね。
ひとりひとり、入り方が違います。
目から
耳から
感覚から
それぞれにちがうのです。
今回は草場さんのカード「観音カード」を使ってアート。
一枚ひいて、いまのメッセージを受け取っていただきました。

そのカードの絵から
言葉から感じたものを感じたままに描いていく。
自分に描かせてあげるのです。
その中で出てきた言葉が
「わたしはカタチを描かないといけないと思い込んでいたんですね」。
かたちのない心に、ゆれうごくこころに
かたちのない心に、ゆれうごくこころに
かたちを持たせることは難しい。
「絵を見て、心に響いたものは何ですか?」
すると、心に響いたものは、色合いでした。
美しい色がまざりあって、とけあっていく様子。
やさしくて、あたたかくて。
「その感じた色合いを自分に描かせてあげましょう。」
そうお伝えすると驚いた様子でした。
必要なのは感じた感覚の追体験でした。
自分が受け取ったあたたかさを、今度は自分の指で描き、生み出すこと。
- 絵は、なにかをかかなきゃいけない。
- 絵は、かたちがないといけない。
- 絵は、意味があるものをかかないといけない。
いつから私たちは
分かりやすくて、誰でも見たら分かる、かたちのあるものを描くことが
絵を描くことだと思うようになっていたのでしょうね?
子どもの頃からの教育でそうなったのでしょうか?
もちろんそういう世界はありますが
それだけが絵の世界でも、アートでもありません。
こころを表現するとは
かたちがなくても、色だけでもいい、点ひとつでも、線でも
もちろんかたちがあってもいい。
ごちゃごちゃになってもいい。
こころを描くということは
そういうことなのだと思うのですね。
そういう場を大切にしているのです。
自由にこころを開放させてあげて
こころのままに表現させてあげて
こころを楽しんで、じぶんを楽しむアートの時間。
自由は怖いものかもしれない。
それは勇気のいることではありますが
こころのままに、描かせてあげると、目の前にどんどんひろがっていく心の世界があります。
とてもこころが嬉しくなったり、わくわくしたりします。
「じっとながめて、そこになにがあるのかな?
なにをかこうかな?とお話してくださいね」
なにを描いてもOK。
なにも描かなくてもOK。
正解はない。
答えもない。
自分が踏み出した一歩が自分の道となる。
心のアートはそんな感覚なのです。
こころのアートは自分と対話するためのもの。
第一のアート&コミュニケーションは自己対話。自分自身とお話をすることです。

描きながら気づく今のこころ。
素晴らしい時間をありがとうございます。

アートセッション受付中です。
日時は相談しましょう。
ぜひ、自分のこころをやすめる時間に取り入れてくださいね。
アートでこころゆるめる、こころやわらぐ。
言葉を持たない子どもがアートするまで~体を手に入れる
2024/06/27
嬉しいことがありました。

放課後等デイサービスでのこと。
ゆびまるこは開発された当初からずっと
あちこちの放課後等デイサービスさまでアートプログラムを
子ども達と一緒に取り組ませていただいています。
その中でのできごと。
言葉を発しないこどものアートと成長
ある生徒さんは出会ったときは言葉を話しませんでした。
絵を描く机にも寄ってきてくれません。
声をかけても向いてもくれません。
手を差し出すと逃げられます。
それでもゆびまるこ教室の時は
いつもと同じ流れで始まります。
いつもと同じように声をかけます。
いつもと同じ近寄っては来てくれません。

それがそれが、だんだんと近づいてきてくれるようになります。
そして、絵本に興味をもってくれたときは、
本をのぞきこんでくれました。
「なにをしているの?」という感じ。
カルタを使ってお話をしているときは
手を差し出して、カルタを手にもってくれました。
カルタを使ってお話をしているときは
手を差し出して、カルタを手にもってくれました。
動物カルタだったので、動物の名前を言いながら、カードを渡したりもらったり。
その行動がコミュニケーション。
私とコミュニケーションをとるようになりました。
だんだんと近づいてきてくれました。
そしてみんなが絵を描いている場所に来てくれて、座ってくれました。
だけどクレヨンは初めての様子。
彼はクレヨンを持つ私の手をもって、ぐるぐる動かす。
(まるでコックリさんのよう…)
手を動かす。
色の線が動き出す。
ぐるぐるぐるぐる目の前にいっぱい描かれて行く。
手にクレヨンを持たせてあげて、にぎらせてあげて、今度は私が彼の手をもって、ぐるぐる。
だんだんと力が手に入ってきました。
だんだんと手が動くようになってきた!!!!
「できた!」
ひとりで描けたのです。
自分の手で、自分の意思で、描くことができた!
瞬間です。
次の教室の日。
その日はクレヨンと絵具の日。
「楽しい」と思ってくれたようで、ぐるぐると描いてくれました。
そして、初めての絵具体験。
すると!
絵具を見て、自分で色を選び出したのです。
チューブのふたをあけて、しぼることはまだできなかったので
絵具を出すのは私がアシスタント。
気持ちよさそうに筆をもって色絵具をぬって行きました。
どんどん色が広がっていきました。
彼の世界に色がついたのです。
感動です。
アートで子ども達の発達をサポート。
発達のデコボコはは個性。
それはひとり一人が個性的な発達ですので
それにあわせたスピード、アプローチなどが必要です。
できることが全然違いますし、こだわりも違う。
そこが面白いのですが、個別指導が必要です。
絵を描くことは、体を動かすこと。
自分の体を使う感覚を育みます。
身体感覚や統合感覚。
体をうまくつかえないお子様が多いので、アートで様々な感覚を使っていきます。
その前に「楽しい」と感じていただけること。
それこそが信頼だと思っています。
これからもどんどんアートに挑戦して
世界を自分の手でうみだす体験をしてほしいなと思います。
指でくるくるゆびまるこ。
みんなの手は魔法の手。指で描きましょ。自由に描こう。
まずは体から。そして次は意思のチカラへ。
どんどん成長していく子ども達が素晴らしくて、嬉しい。
まずは受け止めることから、はじめよう。
2024/06/25
こんにちは。


いま、私は奈良県の保育所でレジリエンスプログラムを
幼児さんにさせていただいているのですが
保育の現場というのは、
本当に子どもたちや家族さんと向き合うことがいっぱい。

レジリエンスを育むためのプログラムは
絵本の読み聞かせやゲームなどを通して
子どもたちが心のことを学んでいき、
前向きな行動選択ができる力を身に着けていきます。
それは子どもたちは自分らしく、夢に向かって成長していくための
レジリエンス力の育成。
学習を通して育っていきます。
(ちなみにゆびまるこはアートを通してレジリエンスを育まれるものです)
その中で先生のポジションがとても大切なのですね。
『ファシリテーター』の役割がとても重要。
ファシリテータ―とは促進させていく人。
この場では、こどもたちの心をひらき、声を引き出していく係。
たくさんの子どもたち、性格も気質も家庭環境も違う。
すると当然に反応もまったく違う。
- 「はい」...いい子でいようとする子。
- なんとか正解を必死に探して、答えようとする子。
- 周りの様子を見て、同じことを繰り返す子。
- あえてまったく違う答えを言って反応を見ている子。
- 乱暴な言葉を使って困らせようとする子。
- 全く反応もなく、表情もかたい子。
- 席に座れない子。
- まわりばかり気になって落ち着かない子。
- いろんな子どもたちがいる。
本当に人の数だけ様子も受け答えも違います。
そんなとき、正直、焦ったりする。
(どうやってまとめよう…)
実はまとめる必要はなくて
導くだけでいいのですが
どうしてもまとめようとしてしまう私もいます。

まずは受け止めてあげてほしい。
今日はベテラン先生から素敵な言葉をいただいたのでシェアします。
きっと子育て中のお母さんや、子どもに接するお仕事されている方、
セラピストさんにも参考になるかなと思います。
「なにが出てきても受け止めてあげてほしいの」
それは
違う答えであっても
期待していた反応であっても
子どもたちは声を出してくれているので
「そっか」って受け止める。
「そうだね」って受け止める。
まずは受け止める。
すべてはそこから。
それからファシリテーターが導きたい方向へ導いていくのです。
「じゃ、今日はこれでいくね」と。
まずは受け止めること。
その覚悟が先生には必要なのですね。
これはゆびまるこのアートワークでも同じ。
大切にしていることです。だけど難しかったりする。
日々、チャレンジです。
なにが出てきても
アートはその子自身なので、まずは受け止める。
アートには間違いも、失敗もないので
一緒に考えたり、描くのを見守ったり、サポートしていきます。
時に乱暴な反応や関心をひくための問題行動もあるのですが
それさえも「表現」として受け止めます。
すべては表現、心の声である。
私は「やらない!」「描かない!」という子には
「そっか今日は描かないのね。わかった!また描きたくなったら教えてね」と言います。
するとだいたいの子どもたちが、あとで「描きます」と取り組んでくれます。
正解を求めると、自由を奪う。
これがもしも正解を求めてアートしていたら
子どもたちは安心して、自由に表現することができません。
自分で考えて、決める力を奪ってしまう。
子どもたちには自由を体験してほしいので、
安心して、自由に表現できる場でありたいと思います。
ゆびまるこが目指しているのは、
学校でもなく、家でもない、子どもたちの居場所。
自由に表現して、認めてもらえる場。
みんなちがって、みんないい!と感じてもらえる場。
『まずは受け止めることから』
子どもたちは安心して、思っていること、感じていることを話していいんだ。
自分の気持ち、心を大切にできるようになると思います。
受け止めてもらった子供は、受け止められるようになる。
いろいろなことを受け止める強さは、まずは受け止めてもらう体験から。
いっぱいいっぱい、いろんな絵を見せてね。
いろんなお話しを聞かせてね。
上野先生の初めての養成講座!仲間ができました!
2024/06/25
「ゆびまるこ講師養成講座が決まりました!」




ゆびまるこの上野先生から連絡がありました。
それはとっても嬉しいお話なのです。
お話によるとずっと教室に通ってくださっていた生徒さんが
基礎から学び、これからゆびまるこの活動も考えていきたいとのこと。
きっかけは
「私もバリに行きたい!」だったようですが。
バリの学校でゆびまるこをするというお話があってから
あちこちから、養成講座を受けたいとの声をいただいていました。
きっかけは何であっても
一歩を踏み出されたことが素晴らしいことだと思います。
養成講座1日目。
ゆびまることは?を学び、
心をひろげる、ゆるめる「まるの構成法」で描く。
とてもシンプルでありながら、ひとつひとつに心とのつながりのあるアート。
プロセスそのものがとても大事で
心をゆるめる意味がこめられているものなのです。
講座の写真を見せていただきました。

みなさんとっても楽しそう!
楽しいのが一番ですね。

どうぶつモチーフ。
これも楽しい。

1日目のアート。
養成講座は担当講師と生徒さんが作っていくものなので
スピードもそれぞれ。
1日じっくりと一緒に描いた時間は素晴らしいものです。
心の変化、生み出されて行くアートたち。
かけがえのない仲間になっていきます。
これからみなさまの活動が楽しみですね。

今回担当した上野眞理子先生。
4人の方が、受けてくださり、ゆびまるこを広めて行く、仲間が増えました\(^o^)/
昨年の暮れに、来年の抱負として思っていた、仲間づくり❣️
本日念願叶うことができましたm(_ _)m
願えば叶う。
夢は叶う。
きっとこれからますますの活躍と発展。
楽しみです。
子どもたちの熱い夏!アートチャレンジ~はじめては不安なの
2024/06/22
こんにちは。





心を育むゆびまるこのルパです。
ゆびまるこ摂津のキッズクラスは
夏のアートチャレンジがスタートしました。
毎年夏には、秋にひらかれる
子供絵画展やコンクールに向けて挑戦していきます。
賞を取ることが目的ではありませんが
目標をつこと、
大きな画用紙に自分の世界を描くこと。
自分で考えて、決めて、描くことが大事。
またさまざまな画材や材料、そして描き方に挑戦していくので
子ども達はドキドキ。
「どうしたらいいの?」
「よくわからない」
誰でも初めてのことはみんな同じ。
こどもも、おとなも同じ不安を抱きます。
それが大事な感覚と体験。
「できないから、やだ」と手を出さないのと
「やってみよう!」と手を出すのとでは大違いなのです。
子ども達の思考パターンにもつながりますし、
人生にも大きく関わってくると考えています。
ゆびまるこでは、自由なアート活動を通して
こどもたちの心の根っこ(レジリエンス)を育んでいきます。
こういう不安やつまづきは大大大チャンス!
「…できない」「…不安」「…どうしよう」という思考を
「やってみよう!」「どうやったらできるかな?」「先生が教えてくれるもん!」と
前向きな思考にかえて、行動すること。
その行動こそが子ども達の心の根っこを育てることにつながるのです。
体験が子ども達の自信をつけていきます。
私たちは、子ども達の一歩を見守り、応援していく。
そして「できたね」と一緒に喜ぶこと。
それがとても嬉しいのです。
今回のテーマは「クレヨンガシガシ、スクラッチアート」
はて?なんだ?それは?
絵本『くれよんくろくん』の世界をそのまんま
実際にやってみるのです。

えーーーーーーー!!!!!
最初はわけがわからない、初めての経験なのでびっくりする子ども達。
反応はそれぞれ。
- 「おもしろそう!」
- 「よくわからないけど、お絵描き好き」
- 「これでいいのかな?教えてもらおう」
- 「みんなのをみてからにしよう」

クレヨンガシガシ。
大きな画用紙にガシガシ。
「なにを描いてるのか分からないー」
→はい、いまは、なにも描いていないので、それでよし。

「ハートがいっぱい」
それだけでも嬉しそうなのです。
好きなものを描くって、それだけで幸せになる。

「は!?」
「え??」
くれよんくろくんが登場です!
ガシガシガシガシ。さらにガシガシ。
ガシガシガシガシ。さらにガシガシ。
せっかくぬったきれいな色がくろくんで真っ黒。
- 「もうわからないよー」
- 「えええええーこれでいいの?」
ちょっと悲しそう…。
その感覚はとっても大事。
せっかくぬったのにね。
でもね。

ひっかきスクラッチパワーで別世界が誕生!!!
「うわー!!!!きれい!!!!」
「うわー!!!!きれい!!!!」
ちょっと悲しくなったけれど
別の世界が広がっていくと楽しくなっていく。
子ども達は笑顔でいっぱい。
子ども達の世界が広がりました。
新しい世界が開いたのです。
『はじめてはだれでも不安』なもの。
だけど一度体験すると、不安はなくなります。
これはこどもも、おとなも、みんな同じ。
だからアートでたくさんの体験をしてほしい。
まだまだ続く夏のアートチャレンジ!
ガンバレ!子ども達!
ゆびまるこ摂津キッズ教室(担当:ルパ)
第2土曜日13時30分~15時
第3水曜日15時~16時30分
※ただし会場の関係で変更の場合もあります。
体験1000円。ぜひ挑戦してみてください。
バリ島の小学校でゆびまるこ!②~国も言葉も超えていく!
2024/06/20
こんにちは。ルパです。



パステルを指で描いて
バリ島でゆびまるこの続きです。
私が訪れたバリ島デンパサール市の公立小学校は
おそらく、みんなインドネシア語だけを話す感じ。
先生たちは英語を話す感じですが
とても嬉しいことがありました。

私は「みんなまる!」という幕を持っていったのですね。
担任の先生が、これはなんて書いているの?と。
そこで説明したのです。
そこで説明したのです。
「これは、みんなまる!と書いてあります。
私たちはひとり一人がまる!パーフェクトで、みんなもまる!
みんながつながって、おおきなまる!となっていく」
そんなことを説明しました。
すると先生が感動。
「なんということでしょう!
この子たちみんながまる!なんですね!」と。
子ども達に伝えてくれたのです。
子ども達を思う先生のあたたかい気持ちが伝わってきて
感動したのです。
そして私と先生が話している様子を見て、
こどもたちが尊敬のまなざしで見つめていました。
「やっぱり先生、素晴らしい」という感じ。
先生に対する尊敬がひしひしと伝わってきます。
先生は子ども達を愛し、子ども達は先生を尊敬する。
そこには絶対的な信頼感がありました。
心から、ここでパステルアートができることに感謝でいっぱ。
…となかなかワークにすすみませんが、
ワークショップでは材料と道具が限られていたので
8グループに分かれて開始。
その前に、
まん中で「集合!」
「はーい、今から始めるから見てね」と私。
デモンストレーションをさせていただきました。
描き方説明です。

- 「これはパステルです。はい、どうぞ」
みんな、「パステル!!」
- 「これは網です。はい、どうぞ」
みんな、「あーみ」。
- 「削りますよ。シャカシャカ。はい」
みんな、「シャカシャカ」。
- 「指で描きますよ。くるくる!はい」
みんな、「くるくる!」
気づいたら、いつもと同じ進行をしていました。
それがとても楽しくて、みんなが目をキラキラさせて見てくれました。
あれ?言葉はどこにいった?
私は日本語。みんなは日本語わからない。
だけどしっかりと伝わっているのです。
そこで驚きのできごと。
- 「これは消しゴム!」…みんな知っています。消しゴムは世界共通の文房具。子ども達の筆箱に入っていました。
「消しますね。」
星型の型紙を使って、けしけし。
けしけし、けしけし…。
「さて、できた!ワンーツースリ―!!!」
「さて、できた!ワンーツースリ―!!!」
星★が誕生!!!
………沈黙。シーン
子ども達はシーン。
目の前で起こったことが分からなくて、しばらく固まっていました。驚いていたのです。
そして
「わあ!!!星が出てきた!なんでー!え?どうして??」
拍手がいっぱい。
拍手がいっぱい。

パステルを指で描いて
どんどん色が変化していく。それもミラクルな変化。
そして消しゴムで消すと、そこに星が生まれる。
なにもないのに
星が出た!
まるで魔法を見ているような感覚。
子ども達の喜ぶ顔がとってもステキでした。
これって、日本の子どもも同じ。
子どもたちの反応って同じ。
みんな驚いて、喜んで、わー!!!っとなる。
新しい体験。
それは子ども達にとって素晴らしい体験です。
パステルアートと出会ってくれてありがとう。
心からそう思いました。
さて、次はどんな絵を描き出すのか?
続きます。
バリ島の小学校でゆびまるこ!①
2024/06/20「バリの子ども達にゆびまるこしてくれませんか?」
そんなお声がけをいただき、
「行きます!」即答。
あっという間に決まった、バリでゆびまるこ計画。
しかし旅にはいろいろあるものです。
予定していた学校でのゆびまるこはできなくなったのです。
あれ?
ところが、またも新しい流れ。
旅の間、お世話になっていたドライバーの方のお子様が通っている
地元の小学校でさせていただくこととなったのです。
「私のこどもの小学校でアートしてくれませんか?」
校長先生にお話してくださり、決定。
インドネシアバリ島デンパサール市立小学校
3年生の授業「パステルアートゆびまるこ」。
日本から先生がやってきた!




実現したのです。
授業の日は新月。
子ども達がインドネシアの正装をしてお祈りに登校する日。

女の子は白いブラウスに、サロンという布をまいたスカートに
腰ひものようなものをまいていました。
サロン布はいろいろなデザインの巻きスカート。

男の子は白いシャツに、インドネシアのズボンをはいて、
頭に白いターバンのような帽子をかぶっていました。

校長先生。
パステルアートゆびまるこをさせてくださって
ありがとうございます。
新月のお祈りの日。
こどもたちが小学校に登校。
するとなにやか違う顔がいる?似ているけれど外国人?
恐る恐る近づいてくる女の子。
「ニーハオ?」
うーん残念。グループは同じだけど違うんだよねって言っていたら、
ちがうわよ!って別の子がやってきた。
「アンニョハセヨ!」にこっ♪
惜しい!近づいたけど、違うのね。
その国でもないのって言う。
「私は日本から来ました。ジャパンです」というと
みんな、はて?どこ?それ?と首をかしげます。
どうも、日本は知らないようでした。
私たちもインドネシアがどこだか、島の名前とか
小さな国の名前も場所も理解していないのと同じ。
インドネシアバリ島の子ども達にとっては未知の世界なのかもしれません。
知らない国からやってきた日本人。
子ども達が日本と出会うこととなりました。
「こんにちは」というと、みんなが「こんにちわ」。
「ありがとう」というと、みんなが「ありがとう」。
ファースト日本人、ファースト日本語。
「こんにちは」
次から次へと両手をあわせて挨拶してくれました。
手をあわせること。
相手への敬意をあらわして、挨拶。
日本でも「いただきます」「おねがいします」「ありがとうございます」と手をあわせます。
同じですね。
感謝。
敬意。
共通のしぐさに嬉しくなりました。

スマホが普及するバリでは
「写真とるよー」ってカメラを向けると、みんな最高の笑顔!
ピースは同じですね。
みんな楽しそう。
とっても嬉しそうです。
こどもたちの笑顔は宝物。
国も、文化も、言葉もちがっても
笑顔は共通言語ですね。
笑顔でいれば世界はつながる。みんな幸せになれる。
子どもたちの笑顔を守りたい。
子どもたちの笑顔を見ていたい。
そう思いました。
「バリでゆびまるこ」つづく。
ゆびまるこに関すること、お気軽にお問い合わせください。 ☎ 080-3787-7345 受付時間:10:00〜18:00 |