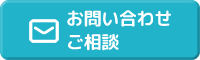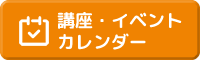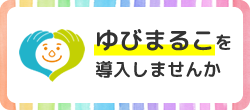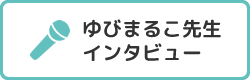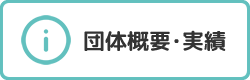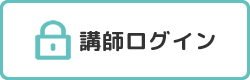- ホーム
- 心を育むゆびまるこ日記
- 子どもの魔法の手「なにつくる?」
子どもの魔法の手「なにつくる?」
2015/11/27先日、高槻にある今城塚古墳のイベントに行ってきました。
この古墳は「ひらかれた古墳」で、中に入って遊べます。
さぞかしマニアックなんだろうと思い
(そういう私も古墳好き)
中に入ってみると、こどもたちがいっぱいでした。
しかも楽しそうに古墳で遊んでいます。

これは紙管。
土管の変わりに紙管でしょうか?
かつて住宅開発まっただ中の頃、工事現場やあちこちにころがっていた土管。
土管は、こどもたちの基地でした。
土管の中に入って、自分たちだけの世界をつくったり、
仲間たちと基地をつくったり、
自分だけの静かな空間だったりしました。
こどもの世界が、土管の中にありました。
今では土管の姿は見られません。さびしいです。
土管が転がっていたら、問題になるかもしれません。
残念。
しかし、古墳の中には、土管ではなく、
紙の管がごろごろしておりました。
紙管は、材料が紙なので、軽いものです。
しかししっかりしている!
土管は動かないけれど、紙管は動く!
ですので、古墳の中で、紙管がごろごろと動いているのです。
まるで虫のように♪
ゴロゴロ、ゴロゴロ。
もちろん、こどもたちが中に入って、ごろごろと転がしていました。
楽しそうに、嬉しそうに、
紙管の虫たちがゴロゴロ、ゴロゴロ。
紙の筒。
乗ったり、立ったり、中に入ったり、
立ててみたり、叩いてみたり。
子どもたちはシンプルなその筒を使って、
いろんな遊びを生み出していました。

紙管トンネルも大人気。
もちろんのぞくと、
こどもたちが、アナゴのように入っていました。
基地であり、トンネルである。
子どもたちにかかったら、大人の想像よりはるか超えた
使い方を生み出します。
天才!
紙の筒。
その使い方はたくさんあります。
こどもたちはいろんな遊びを生み出します。
シンプルなものだからこそ、いろいろ試してみて、遊んでみて、学ぶのです。
遊ぶ。学ぶ。
やってみる、遊びを発見。
その体験が想像力を育て、創造力につながっていきます。
古墳の子どもたちは遊びの天才でした。
大人にとっては不要なものでも、子どもたちの手にかかれば宝物。
魔法の手で様々な機能を生み出して、
宝物に変えていくのです。
みんなもっている魔法の手。宝物に変える力は持っている。
「なにつくる?」
「どうしようか?」
テープの芯やトイレットペーパーの芯なども、
捨てる前にちょっと聞いてみてはどうでしょうか?
そこから子どもたちの無限の想像性は始まります。
その言葉がけが想像力を育てる鍵です。
どんなものが生まれるかな?
わくわく、楽しみにしていてくださいね。
そして一緒に「できたね」って
喜んであげてくださいね。
この古墳は「ひらかれた古墳」で、中に入って遊べます。
古墳の中で、古墳のテーマの、古墳イベントです
さぞかしマニアックなんだろうと思い
(そういう私も古墳好き)
中に入ってみると、こどもたちがいっぱいでした。
しかも楽しそうに古墳で遊んでいます。

これは紙管。
土管の変わりに紙管でしょうか?
かつて住宅開発まっただ中の頃、工事現場やあちこちにころがっていた土管。
土管は、こどもたちの基地でした。
土管の中に入って、自分たちだけの世界をつくったり、
仲間たちと基地をつくったり、
自分だけの静かな空間だったりしました。
こどもの世界が、土管の中にありました。
今では土管の姿は見られません。さびしいです。
土管が転がっていたら、問題になるかもしれません。
残念。
しかし、古墳の中には、土管ではなく、
紙の管がごろごろしておりました。
紙管は、材料が紙なので、軽いものです。
しかししっかりしている!
土管は動かないけれど、紙管は動く!
ですので、古墳の中で、紙管がごろごろと動いているのです。
まるで虫のように♪
ゴロゴロ、ゴロゴロ。
もちろん、こどもたちが中に入って、ごろごろと転がしていました。
楽しそうに、嬉しそうに、
紙管の虫たちがゴロゴロ、ゴロゴロ。
紙の筒。
乗ったり、立ったり、中に入ったり、
立ててみたり、叩いてみたり。
子どもたちはシンプルなその筒を使って、
いろんな遊びを生み出していました。

紙管トンネルも大人気。
もちろんのぞくと、
こどもたちが、アナゴのように入っていました。
基地であり、トンネルである。
子どもたちにかかったら、大人の想像よりはるか超えた
使い方を生み出します。
天才!
紙の筒。
その使い方はたくさんあります。
こどもたちはいろんな遊びを生み出します。
シンプルなものだからこそ、いろいろ試してみて、遊んでみて、学ぶのです。
遊ぶ。学ぶ。
やってみる、遊びを発見。
その体験が想像力を育て、創造力につながっていきます。
古墳の子どもたちは遊びの天才でした。
大人にとっては不要なものでも、子どもたちの手にかかれば宝物。
魔法の手で様々な機能を生み出して、
宝物に変えていくのです。
みんなもっている魔法の手。宝物に変える力は持っている。
「なにつくる?」
「どうしようか?」
テープの芯やトイレットペーパーの芯なども、
捨てる前にちょっと聞いてみてはどうでしょうか?
そこから子どもたちの無限の想像性は始まります。
その言葉がけが想像力を育てる鍵です。
どんなものが生まれるかな?
わくわく、楽しみにしていてくださいね。
そして一緒に「できたね」って
喜んであげてくださいね。
関連エントリー
-
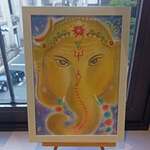 「好き」って最高!
「たくさんの絵を見せてくれて、ありがとう!」そう言ってもらって、びっくりしたルパです。まさか、そんな感想をいた
「好き」って最高!
「たくさんの絵を見せてくれて、ありがとう!」そう言ってもらって、びっくりしたルパです。まさか、そんな感想をいた
-
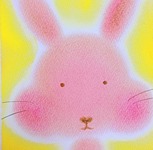 アートで、心を休めましょう。
こんにちは。心を育むパステルアートゆびまるこのルパです。今年にはいって、インフルエンザにかかりひたすら寝ている
アートで、心を休めましょう。
こんにちは。心を育むパステルアートゆびまるこのルパです。今年にはいって、インフルエンザにかかりひたすら寝ている
-
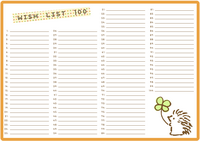 書くと、叶う!ウィッシュ・リストを作ってみよう!
こんにちは。心を育むパステルアートゆびまるこのルパです。私は毎年最初に「今年のウィッシュリスト」を作成します。
書くと、叶う!ウィッシュ・リストを作ってみよう!
こんにちは。心を育むパステルアートゆびまるこのルパです。私は毎年最初に「今年のウィッシュリスト」を作成します。
-
 夢を「描く」練習。
おはようございます!心を育むパステルアートゆびまるこのルパです。今日は夢を「描く」練習についてお話しします。夢
夢を「描く」練習。
おはようございます!心を育むパステルアートゆびまるこのルパです。今日は夢を「描く」練習についてお話しします。夢
-
 第11回せっつまちゼミ、受付開始!
こんにちは。心を育むパステルアートゆびまるこのルパです。じゃーん!2月です。まちゼミの季節がやってまいりました
第11回せっつまちゼミ、受付開始!
こんにちは。心を育むパステルアートゆびまるこのルパです。じゃーん!2月です。まちゼミの季節がやってまいりました
ゆびまるこに関すること、お気軽にお問い合わせください。 ☎ 080-3787-7345 受付時間:10:00〜18:00 |